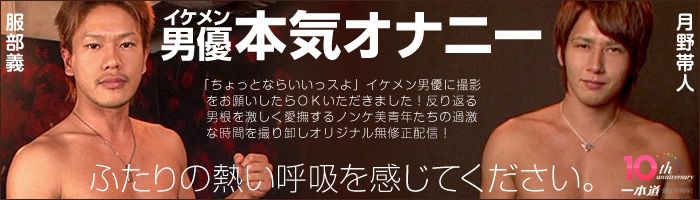�M�Y�̉��_�ɂ��������܂������A
���̎��_�ʼnƍN��łڂ������o�����Ǝv����ł���
���v��̔s�k�͂����܂ŋǒn��ł����A
���̂܂܂����ƔS���Ă���A�ƍN�R�͓�����������Ǝv��
�G���̃A�z�̂����ŁE�E�E�E�B
���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��Ǝv�����A�W���n�ɂȂ�̂͊m���B
�푈�̏��s�����߂�̂͂�͂荑�͂���B
�Ă������A�M�Y������ɍu�a�������ƂŁA����E�D�c�A���R��
������������Ƃ�܂��B
�łڂ��Ȃ������̂ł͂Ȃ��A
��̐l�ގ��W�Ȃ�������Ȃ��B
�D�ꂽ����̕��͂�g�ݍ��݂��������̂����B
( �L߃�߁M )9m
�M�Y�����_���ĕ��͂Ɩ������킬���������瓮���Ȃ��Ȃ�Ύ�芸��������ł悩�����̂��낤
������˃��x�̍Č���_�����G�g�̍낤�B
�ƍN��ނ肾���A�{���Ƌ������ɂ���Ƃ����B
�������ƍN���������������B
�G�g�͔����Ă�����H
����������͖����D�c�Ɏd���Ă������������A�����͌����Ȃ�������Ȃ��������B
���̎��_�œ����̎��ĂȂ��G�g�R�����邾���ŏG�g�͎��t��������B
������ɂȂ�����D�c�Ƃ̓����ɃT���Ă�肳��Ă���G�g�R�����Ă����̂͊m���B
�����Ċ�{�I�ɗ~�Œނ��Ă�����������ˁB
���オ���Ȃ��G�g�͂悭����Ă���ˁH
�r�c�����ɗ������ꂽ�炨�d��������������ˁB
�ȂM���̌Z�킪�M�Y���������ďG�g�ɂ������Č������Ŕ���������B
�Z��2�����̉��܂Œނ������厩���̕��j��r�c�����̋����ŋȂ�����Ȃ��������Č����Ƃ���ɏG�g�̐h�����������B
����Ɍb�܂�k���Ɠ�����g��Ō�ڂ̗J�������Ă����ƍN�ɔ�ׂ��璷����ɂȂ������������̉\���̍����G�g�͈��|�I�ɕs���B
���Ə��q�E���v����ĕ\�����ɂ͐D�c�M�YVS�H�ďG�g�ʼnƍN�͒P�ɓ����̋b���Ă�������Ȃ������H
�A���Ͽ
�ǂ��l�߂��Ă��Ƃ����̂��j������킩��炵���˂�
�Ȃ�Ďj���H
���a�c�N�j���̐푈�̓��{�j15���̏��q���v��̏͂ɏ����Ă�������B
������Ɠǂ����Ȃ�Ŏj�����͊o���ĂȂ����ǎO�͂̎��̏Z�E�̓��L���������ȁB
�d�@���x�T���Ă݂�B
���ɋI�B�̒n���̊����������ŁA�G�g�����̂��G���ł���a��ɂ܂Ői�o�����肵�Ă���B
�t�ɉƍN���̃f�����b�g�́A������ʕ��͂̈��|�I�ȗB
���̌�����ʂł��鏬�q�ł̒�����Ƃ����W�J�́A�ƍN�̖]�ݒʂ�̓W�J�������낤�B
�����A�G�g�̑�NJς͉ƍN�̈������s���Ă���A������ʂ��ɂݍ��������A���g�̍ŋ��̕��c���G���Ɏw�������ɐ����ʂɓ����A�D�c�̂̔��Z�A�ɐ��̖w�ǂ�D���Čp��s�̏ɒǂ�����ł���B
���ɖ������m�̐푈�ƕ]�����Ă������A���M���x�z���̔��Z�����A�r�c���̋��A���߂������́A�ї��A�O�c�A�㐙���i���̎��G�g�̖����ɂȂ����喼�͂��������Ɂj�S���̑喼�ɂ�������O����r�A���ɂ����ďG�g���ƍN���������킾�����B
�r�c�A�X���A�U�X�ɔj��Ƃ����叟���ɂ��ւ�炸�ŏI�I�ɔs�k�i�L�b���쒆���n�̔����ɐ��������I�ɖL�b�x�z���Ɂj�����̂́A�헪�I�Ɉ��|�I�Ȕs�k�����ɂ������Ă�������ł���B
�����Ęa���ȍ~�A����ɘA�g�����喼�B�i�l���A�z���A�I�B�j�͂��Ƃ��Ƃ��e���j���ꂽ�B
�{�P��O�̏G�g�́A���{�j��ŋ��N���X�̌R���w�����A�����Ƃ������Ǝv���B
�������ƍN�̔s�k��s�k�Ɍ����Ȃ�������r�����B
��ɓV�������B
�^�����͂̃E�`����
�^��������ΓV���͎��Ȃ�
���̃V���{����Œ����͏G�g�{���Ɛ������
�t�ɏG�g�̔��ĂŁA�ƍN��U�������������ɂ��邽�߁A�킴�Ƃ̂�̂�N�U�������̂��낤�B
�������ƍN���ꖇ���Œ�����R�����j���A�G�g�ɕt�����錄��^���Ȃ������B
��p�@��������̃L���ɂȂ��͂܂�)���ǁA�헪�@���̏d�v����
�F�����Ă������̎��s��(�⋋�̐��̊m��)���������B���G�Ə��ƂƂ���
���̕�������ɖ��ŏ����Ă�̂����炻�̔\�͔͂�}���Ǝv���B
���q���v���ł͂Ȃ��ɂ��̓��ӂȂ͂��̋@����ʼnƍN�ɒx����Ƃ���
�̂��낤���B�V�����قڎ蒆�Ɏ��߂Ă��G�g����ԋ���Ă��̂́A
���͐�ʼn^�����ƍN�ɔs�k�������ƁA�D�c�����p�����咣����M�Y��
���Ƃɏ������Ȃт��Ƃ����V�i���I�B������A�ƍN�Ƃ͖����Ɍ����
���Ȃ��ĐM�Y�����܂点��悩�����B��̉�����ʕʓ����͌���
����������A�܂���点�Ă݂邩�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
���q�Ɍ��炸���叫�̈ӂɔ����ĕʓ�������U�߂ɂ�������Ď��Ԃ�
�����Ƃ������Ƃ͌��\����܂���(�ւ����A����Ȃ�)�B������
�ʓ����̑叫���C�}�C�`�N�������Ƃ������ʂ̂ق����悢�Ǝv���B
�`�̏�ł͏G�g�ɏ]���Ă͂��邪�A����I�ɂ͏G�g�Ɠ��i�B
����ɁA�M���Ɛb�c�̒��ł��ŌÎQ�ł���A���̍P�����M�Y��M�l�ł͂Ȃ�
�G�g�ɂ��Ă�����Ă����̂͑傫�ȈӖ������킯���B
���̍P�����咣��������������G�g���f�肫���킯�ł��Ȃ��A
�܂��A���Ď��̂͂���قǖ��̂�����̂ł͖����������ǁA
��P��O��Ƃ����i�R�Ƃ͎v���Ȃ��o�H�A�v�����n�߂��U���I
�Ȃǒt�قȍs������ŁA����͎w�����鏫�̖�肾��B
�O���G���͂�����Ŏ�����R�ōP��������ł��ď��߂ĉƍN�̊�P������
�m��قǂ̎U�X�ȏ�ԁB
�j���قɂ͐F�X���������ǁA���ɋL���Ɏc���Ă�͈̂�x���C�p���Ƒ哛�ƒZ���B
�n���ɂ͋|���ꂪ���������ǁA�|����Ȃ��āA�Γ�e�����Ă݂�����ˁB
���̒n���ɂ͖_�̎�Ȃ�S���ɓ`��镐�p�i�H�j���������炵���A�S�C�A���A�㓁���������B
���ƁA�r�c�e�q�̒˂��Q�B
���Ȃ݂ɕ����˂͂�����ƌ������痣�ꂽ�Ƃ��ɂ���
�s���ĂȂ����ǁA��͕ʂł����ɂ���炵���B
��
���������ُ��肵�Ă݂���
�������ƍN�̐��U�ōō��̊撣�����������ł�����B
�ƍN����̖���ƕ]��������������邪�A���쑊��ɂ͒����ŐN�������Ă��邵�A���c�ɂ͖��ŕ��������Ă���B
�փ����͉��������߂����A���\�͂Ƃ������͒���������������ہB
�^�c�[�㐙�ɂ�����Ƃ��������������������A�M�Z�̗L������䖝��ׂ̏������܂߁A���̎����̓���Ƃ͖{���ɋ��������B
�֓��ڕ��ȍ~�A����Ɛb���狭���͖����Ȃ��Ă��܂��B
����ƍN���U�ō��̐�́A�L�b�G�g�̓V���������C�ɉ�����������ł��������B
�������ƍN�̐��U�ōō��̊撣�����������ł�����B
�ƍN����̖���ƕ]��������������邪�A���쑊��ɂ͒����ŐN�������Ă��邵�A���c�ɂ͖��ŕ��������Ă���B
�փ����͉��������߂����A���\�͂Ƃ������͒���������������ہB
��킪���ʋ���������ł͂Ȃ������悤�Ɏv���B
�A���^�c�[�㐙�ɂ�����Ƃ��������������������A�M�Z�̗L������䖝��ׂ̏������܂߁A���̎����̓���Ƃ͖{���ɋ��������B
���̌�̊֓��ڕ��ȍ~�A����Ɛb���狭���͖����Ȃ��Ă��܂��B
����ƍN���U�ō��̐�́A�L�b�G�g�̓V���������C�ɉ�����������ł��������B
�ƍN�͐푈�̏I��点�����l���Ă̎Q�킾�낤���A���������ėɂȂ�����
�M�Y���̂ĂāA�G�g�ɓ�������ΐӔC��M�Y�ɉ������a�r���ł���Ǝv��
�D���ɂȂ�Ύj�������M�Y�ɘa�r������A����͂���ŗǂ����Ċ����ŁB
�̐S�Ȃ̂͏G�g���ƍN���A���ڑΌ��͓O�ꂵ�Ĕ��������B
��ʔ�ׂ̂悤�Ȑ킢�Ȋ����B
���݂����P���Ă��˂��̍���
���x���Ⴂ�ȃR�R�E�E�E
���킢��
���q���v��Ȍ�́A���҂̋삯�������ǂ��A�}�j�A����O������
���܂��Ɏ��������ł����Ȃ������Ƃ̉��g�Ȃ�ĉƍN�ɂƂ��Ă��̂��������J����B
���q���v��ʼnƍN�͏G�g���l�̎q�Ȃǂƒ������Ă邪�A������l�̎q�̒����𐳎��Ɍ}���Ă���̂�
�ǂ�������������̂��H��
����͏G�g�l�Ȃ̂���
���͂��猩����j�i�̑ҋ�����
1���q���v�蓖���̘b���ł���Ȃ�G�g�͎��������p�œV����������̂����o���Ă���
����̐����ȌR�c�����ƍN�Ɨ����ŐK����U�鎩�w�c���ڂ݂Č���ɓ��ݐ����ꍇ
�ƍN���ɕt�����̂����낤�Ǝv������͔�����
2�܂��V���l�Ƃ��ĔF������Ă����O�A��F����̋~���v���Ɍ�����Ȃ���Ȃ炸����Ɩ{�i�I�Ɍ�킷��킯��
�͂����Ȃ������i�������Ƃ��Ă����Ԃ�������j
3���đO�Ƃ͂����G�g�̎�̓����҂ł���ƍN�͏G�g��肠���炩�Ɋi����ł���A�ƍN�ɋ�������
�M���⎙�ւ̓����̉ƍN�̍s���ł͓����͉ƍN�ɂ�������
4�L�b����������͂Ȃ����瓿��Ƃ͔�剻��
��������Ǝ���o���鑶�݂ł͂Ȃ��Ȃ����悤����
�L�b�͓���ɕ�����ׂ����ĕ�����
���m
�T�^�I�ȉƍN�~
�����ƍN�~�����ǂ���Ă�ȁB
�G�g�ɏ����Ă��Ӗ����Ȃ��ƍl�����Ǝv���B
���̏�ʼn��ɏG�g������A�����܂����Ĕ��Z������܂Ői�o���Ă��A�ʂɑ��̒n���喼���ƍN�ɏ]����������B
�퍑���i�������Ă����������B
��������K���Ɉ��������Ȃ�a�r���āA�����������G�g�ɔ�����鎖�ŁA���傫�ȉe���͂���ɓ��ꂽ��
�����ĕ�����Ƃ��������L�邵�A�����ď��Ƃ��������L��B
���̂�����̏����ƍN�̏�肢�Ƃ��낾�B�G�g��M���ɂ͌����Ă��������Ǝv���B
�n���Ȃ�Ă����������H
�˂Ȃ�Ă����������H
������~�������ɂ����Ȃ�
�ŁA�G�g����ŗc�������̐Ղ��p�����̂��@�ɓV����D��������
�V���l�ƂȂ�������������ɍl���邩�珬�q�̐킷��ƍN�̐[�d�����Ƃ��Ȃ��ƌ����o��
���̏ꍇ�͏G�g�̐b���ƂȂ邩�ŖS���̓�ґ��ꂾ��
�܂��A�������܂ł��������ō~�������̂��������ƍN�Ƃ������Ƃ��납
�M���݂����ɖ��m�Ȉӎu�������Ă����킯����Ȃ��B
���̒ʂ�
���ڂ��邽�߂ɁA�킴�Ƃ��������������Ă��̂����m��Ȃ��ȁB
���̂��ƁA�����Ƃ����ׂ����A�⎙�̋P�����ƍN�̖��ƌ��т����肵�Ă�̂��䂾�ȁB
���̐킢�ŗ��������Ă邩��ȁB
�W�߂̊����������G�g�R����C�ɓƍِ����ɂȂ��Ă�B
�����Ȃ������ʼn̂܂���n���̎�ɂ����Ȃ��ƍN
�G�g�����������V����̕����Ǝ����������グ�Ă���A�ƍN�����͂Ƃ����������Ƃ��Ă͎�������Ԃƌ���������
�G�g���o�c�����Ȃ��ĐȂ��O�����Ƃ��B
�y�K�����z ���e�j�����ƂŔ��C�A�x���܂ނR�l���� �@���q���v��̐킢�@��3
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1179396729/
�퍑����͐��E��̌R���卑�������̂����͂P�l�̗��Ă����肷��ۂP���������Ă����Ƃ��Ȃ��悤�ł́B
�x�@���L�b�R
���f���Ă�������SAT�̂������X����
���Ă�����͂��܂ł������܂���B���������A������͓��{�ł͊F���ɋ߂��ł��B
72����R�ƖL�b�R�ɗႦ��̏�肢������R�͖����悭�s�����Ă������
���܂�s���ĂȂ��B����R�ƖL�b�R�t����Ȃ��ł����i���̐w�݂����Ɂj�B
�G�g���ƍN������̉A����Ȃ����Ă���ł��낤�ō��B
�Ɛl�����������A���������Ȃ��̂ɘU�邵�Ă��Ӗ��Ȃ��B�吨�̌x����
��͂���Ă�̂�����B�Ɛl�̔n�������悭�킩��B
�ɑi������\�������邩����{�x�@������ŔƐl�˂���Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǖ���
�͂����ōς܂��Ă����Ȃ�Ƃ����ɉ������Ă�B
�v�ǂł��Ȃ����ƂȂ��炷���˓��͂ł��邵�ˁB
�����A����͐퍑����ł͂Ȃ�����B
���̐킢�͉ƍN�̕��킾��
�G��O�A���@�䕔���e�A���X���������ċ@��҂����킯����
�������Β������قlj������N����\�����������킯����
���Ƃ╺�̔�J�̖�������킯��
�ƍN�͂���ɓq���Ă��낤��
���������Ă��M�Y�̂����ɂ��ďG�g�ɐb�]��������킯����
�t�Ɍ����ΏG�g�͈ɐ�����Z�𐧈�����]�T���������킯��
�a���̏������G�g�L���Ȃ킯����
�ǂ����ɂƂ��Ă��A�����푈�ł������̂͊m��
����ȍ~�̓���̐푈�ŗL���Ȃ̂͊փ��������ǃA���͊��S�Ȓ����ł̏���
����匴�{���̑劈��@���ꂩ��挩���邱�Ƃ́E�E
����͂Ƃ������A�o�w�����ƍN�������ڎw�����̂͑�_�邾�����̂ł͂Ǝv���B
�����āA�ƍN�͒��哹�Z�����쑤�o���ŏG�g�R�Ƒΐw���悤�Ƃ����̂ł͂Ǝv���B
�ړI�͂����܂ŒZ������ł̏G�g�Q�B�Ƃ��낪�r�c�����R�Ō��N�������߈����Ԃ��H�ڂɁB
���̂�����ʼnƍN�̓v������ύX���Ē��ΐw�ł̃|�C���g�҂��ŗL���ȏ����ł̍u�b��͍�������Ȃ��Ȃ����B
�G�g�͏G�g�ŁA�����k�����C�ɂȂ��đ啺�͂̓������s�\�ȏ�ɒ��ΐw�͔��������Ƃ���B
�����ŐX�̍�ɏ�����̂��^�̐s���B�@����Ŏ哱���������G���ʓ����͉�ŁB�G���͖������������̖̂؉��ꑰ�͏��ŁB
�̐S�̉ƍN�͂������Ɛ�ꂩ��P�ނ��Ă��Đ����̗l���B
�G�g�ɂƂ��Ď������̂��葽���ē�����̂̂Ȃ��킢�B
����ȏ�̒��ΐw������邽�߁A�M�Y�ɂ��Ȃ�L���ȏ����ł̌��������|���ĉƍN�ɐw���������邵�����������B
�Ƃ��n�}�����Ȃ���z�����Ă݂��B
�͂��͂�
�ϑz�����������ɂ���
�ɂݍ������M�Y�P�Ƙa�r���ƍN����
�����ƍN�Ƃ��a�r�ɂȂ����Ǝv����
���肷���łڂ���Ă��ȁB
�ɂݍ������M�Y�P�Ƙa�r���ƍN���́��ƍN�u�a�������{�̖{�i�I�ȕ����Ƒ��s
���Z�����ɋ��D�c�Ɛb�c�ł��L�͂Ȓr�c�P�����z�u�����
���ʓI�ɁA�G�g���̑������قږ�����ɁA�Z�����̖��ɏo�����̂�
�o���߂��̂悤�ȋC�����邪�B
�֓����ʂ���i����叫�Ƃ���A����E�k���R����̉����ꂽ�̂���
���̂܂܁A�G�g����Ɩ���l���ɍ����o���Ă܂ŁA�ƍN�����_�Ȃǔn��������������
���͂ʼnƍN��ׂ��Ă���Ηǂ������̂�
���@�䕔�A�G��Ꝅ�O�A���X�ȂƘA����������ΏG�g��͖Ԃ�����
���ɎG�ꐨ�͐ϋɓI�ŁA�����̑�R�Ŗk�サ�Ă���
����͒����ꎁ���}�����A���j�T��Ƃ����叟���Ė��͉�������
���A�Ŋ̐S�̖{��ɍ��c�E�I�{��Ƃ������G�g�q�����̐��s���Ԃɂ���Ȃ�����
���������ɂȂ����̂����̉e����
�ƍN�P�̂Ȃ�Ƃ������A���G�g���͂����O���Őb�]��������͂ŋ����������肵�Ȃ��炾����������ƂĂ������Ȃ�
���q�E���v��̐�p�I�����ɂ��ƍN�̖��͈�C�ɍL�܂�A�G�g������Ɏ�o���͂ł��Ȃ��Ȃ���
���ꂪ��ɉe�����y�ڂ��A�L�b�����ő傫�ȗ͂������Ђ��Ă͊փ�������̐w�ɂ��e������
�ƍN�����ďG�g���ł͂Ȃ��ɂ���O�����B
����������A���G�g�����`�����ƍN���t�]���Ď������蓾��B
�����Ȃ��������Ă����邾��c
�E�G�g�̖���������A�ƍN�̖����オ�����i�\�Ƃ����̂͋��낵������ŁA���{�̒[�����܂œ`��鍠�ɂ͂ǂ��Ȃ��Ă邩�킩���j
�E�ƍN���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����i�֓��]���͋���̍�A���ۂ̂Ƃ��뎸���ȁ@�ŏI�I�ɖL�b�ƖŖS�̈���ɂȂ����j
�E���Α叫�R�ɂȂ�Ȃ��Ȃ����i�H�j
�M�Y�A�ƍN���͂����[�����Ă܂����B
��������P���ڂŏ�U�߂��Ă鶽�������w�����Ă镔����
�ǒn��Ŕj����������ĂȂ�Ȃ�H
����Ɍ����A�ƍN�͒P�ƂŗB�ꂻ�ꂭ�炢���������킪�����ʂ̐퉺�肾���ȁB
���P�ʂ̕����̉B�������ړ��Ȃ�ĕs�\�ł���ȏ�
�A������N���邪�������痎�Ƃ��Ȃ��Ƃ܂�������
��w���Ւf�����
�킴�킴�G���̏�̖ڂ̑O��ʉ߂��郋�[�g��I���������_�Ŕn������B
����܂ł��ׂĂ̏�𗎂Ƃ��̂��H
���X��͂��������̂�j�~����ׂɗv�Ղɒz�������̂Ȃ���B
�܂蕁�ʂɍl����Ȃ��C�ɉ�����Ղ����肾�����Ƃ��������^�킵���B
�����炭����E�D�c�R�̌���ɐi�o���āA�������̌`�ɂ�����h������Ƃ��A
���邢�͊փ����̍ۂɉƍN���s�����Ƃ�����悤�ȁA�G�̖{���n�ɐi�R����ƌ����āA
�G�R���邩�炨�т���ׂ̍�킾�����̂�������Ȃ��B
�����������Ȃ�n�������㑊��̓������ύטR�炳�����ӂ���͂��ŁA�����̈�R�Ȃ�܂������ƍN�{�����w���o���̂ɋC�t���Ȃ����Ă��肦�Ȃ��B
����̐M�����Ȃ��悤�ȃG���[�ɕ֏悵�ď����������Ȃ̂�
TOP �J�e�ꗗ �X���ꗗ �폜�˗� ��
�E�@���̃X��
�y�l�E�Ɓz��F�ꑰ�����y�O��E�ዷ�z
���������ƁA���܂ɂ͓瓇�������X��
�}���𖼏��̂悤�ɐ�������X���R
�y�L�\�������Ɓz�M�Z�l�叫�y�M�������z